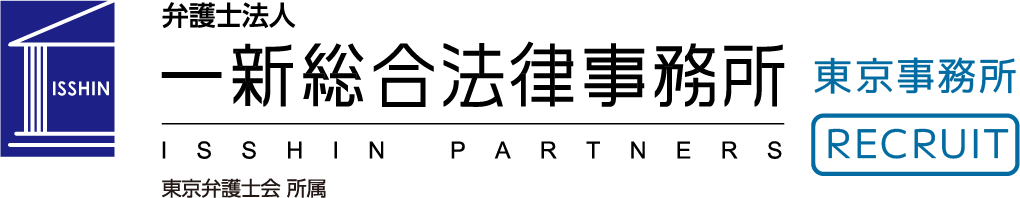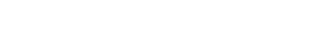キャリアと事務所について
―― どのような経緯で一新総合法律事務所に入所されたのですか?
東京三会主催の修習生就職合同説明会で、ブースで事務所の説明を受けたことがきっかけです。
―― 一新総合法律事務所を選んだ理由は何ですか?
新潟を中心とする事務所であり、地域柄あまり自分に縁のない事務所かと当初は思っていたのですが、地に足を着けて堅実に成長しつつも、クラウドシステムの本格的導入など、新しいものを積極的に取り入れる姿勢が魅力的に映ったためです。
現在では多くの事務所が同様のシステムを導入していますが、私が就職活動を行っていた当時(2017年)では、このようなシステムを利活用していた法律事務所はかなり少なかったと記憶しています。
また、選考過程において、かなり細かな点(待遇面)に関する質問にも誠実にお答えいただいたことも好印象であったため、当事務所を選びました。
―― 入所後、どのような業務に携わっていますか?
東京事務所は、不動産関連業務に特化した事務所ということもあり、不動産に関連する業務を中心に携わっています。
このように書くと、経験できる業務分野が狭いのではないか、という印象を持たれてしまうかもしれませんが、不動産賃貸借、売買、建築紛争など典型的な不動産案件以外にも、離婚(自宅の財産分与)、相続(所有不動産)の承継等、皆様がイメージされる典型的な業務分野にも密接に関係するため、イメージよりも幅広い業務に携わっております。業務の形態としても、交渉、調停、訴訟、執行等、幅広く経験を積めております。
特に、不動産中心で携わっている関係上、差押え・執行については、通常の弁護士よりも多く携わることができているのではないか、と思います。また、当事務所には多数の顧問先もおりますので、一般企業法務についても多く携わっています。契約書のレビューや法律相談、クライアントからのクレーム対応等、典型的なものから、業法規制(宅地建物取引業法・賃貸住宅管理業法等)への対応、不動産の新規事業に関する法務サポート等、不動産という分野を軸に、多種多様な業務に携わることができています。
仕事のやりがいとチャレンジ
―― 最もやりがいを感じる瞬間はどんな時ですか?
依頼者が抱える様々なトラブル・紛争が終了したときです。
ご依頼を受ける案件・相談の多くは、依頼を進めていく中で、当初依頼者が想定している以上の問題点、ハードルが発見されることもあり、また解決までに長期間を要することもあります。依頼者としても(さらに言えば、弁護士としても)、全てが思い通りにいくことはなかなかないわけですが、だからこそ案件が終了した際には、やりがいを感じられます。
必ずしも依頼者満足のいく形で終結することばかりでもなく、結果によっては落ち込むこともあるのですが、そのような場合でも依頼者から対応につき感謝のお言葉をいただくこともあり、結果も重要ですが、それに至る過程についても依頼者には見ていただいているなと思うことは多いです。その意味では、最終的な結果の良し悪しにかかわらず、やりがいを感じられているのかもしれません。
―― 印象に残っている案件について教えてください。
選ぶのはなかなか難しいですが、1年目から数年間対応していた建築訴訟の事案については、交渉から訴訟提起、その後の交渉含め、四苦八苦しつつ、パートナー弁護士(理事)の助けも借り、最終的に和解成立に至った点は、とても印象に残っています。
また、不動産案件以外でも、高額の債権回収事案についても、印象に残っています。仮差押えから訴訟まで、手続を一通り全て行うことができたこと、貸金の回収という一見単純な事案でも、事案を精査することにより、様々な法律上の論点が存在することを実感することができました。また、法的な部分以外にも、「法律上の請求の認容可能性」のみならず「実際の債権回収可能性」という点なども常に意識しないといけない等、その後の事案対応において、様々な形で活きています。
―― クライアントのために心がけていることは何ですか?
「法的な正しさ」に固執しすぎない、という点は常に意識しています。弁護士としては、上記の点についての検討を中心的に行う訳ですが、その結論が依頼者にとって必ずしも満足する結果になるわけではありません。
例えば、時間をかければこちら側の請求が実現する見通しがある事案であっても、依頼者が早期解決を強く望まれている場合も往々にしてあるわけで、このような場合に依頼者の意向を尊重することなどは忘れないようにしています。
ただし、依頼者の意向が、法的な整理を必ずしも前提にしていない場合も多くありますし、また弁護士との協議の上決めたい、という意向をお持ちの場合も多いです。そのため、依頼者の意向・要望と異なる場合であっても、依頼者のご判断の前提として「法律上の整理と見通し」「この点を踏まえた弁護士としての意見」は、きちんと伝えることは心がけています。
「DX・AI」に関する取り組み
―― ITなどを導入した業務の中で、どのような変化や利点を感じましたか?
コロナ禍以前、私の入所時点でクラウドによる案件管理・共有、web会議システムを利用したオンライン会議の実施等はすでに行われており、ITの導入に積極的な事務所でしたので、入所時点から現在まで、継続してITを利用した業務対応を行っております。
現在事務所で利用しているクラウドサービス(LEALA)の開発者が事務所の弁護士(東京事務所所長・大橋弁護士)であったため、入所後も事務所内の意見を集約し、様々なカスタマイズ・アップデートがなされており、さらなる業務効率化を実現しています。
また、AIの業務活用にも積極的であり、現在、私も ChatGPT や Gemini をはじめとする各種AIをすでに導入・活用しています。このほかのAIサービスについても、順次導入を検討しているという話も事務所内で出てきています。なお、AIの業務活用においては、個人情報の流出等が懸念されるところですが、当事務所では独自のガイドラインを制定しており、所属弁護士は当該ガイドラインに則ってAIを活用しています。
―― 弁護士でDXやAIを活用することに対して、どのような可能性を感じていますか?
業務の効率化の促進という点はもちろんかとは思いますが、この点を通じて「弁護士の本質的業務」に弁護士がより注力できる環境がAIにより実現できるのではないかと思っています。
AIは日々進化しており、回答の精度も上がっています。まだまだ誤りを含むところもありますが、将来的にはかなりの精度ある回答が返ってくるのではないかと思います。
ただ、AIは「問いに対する回答」を得るツールではありますが、「紛争・トラブルの落とし所を見つける」ところまではしてくれません。最近はAIを利用して暫定的な見通しを調査されている相談者・依頼者もいらっしゃいます。回答内容自体は法律上ある程度正しいものではあるものの、実際の問題解決には「経緯を踏まえたご自身の感情」「相手方の主張・スタンス」「交渉・訴訟等の手間や費用」等、法的な見立て以外の様々な要素を踏まえることがどうしても必要といえますし、この点をきちんと押さえて、初めて紛争・交渉を調整・決着に導くことができるものといえます。
このような紛争・交渉を相当なラインで調整・決着させることが「弁護士の本質的業務」であり、この点は、AIが日常的に活用される今後の社会においても、日常的に交渉・紛争案件に携わる弁護士としての知見がこれからも求められ、よりこの点に注力できるのではないかと私は思っています。
ワークライフバランスと成長
―― 仕事とプライベートのバランスはどのように取っていますか?
業務の進め方や打合せの調整、受任の可否の判断含め、自分の担当する案件については広い裁量がありますので、ワークライフバランスは取りやすい環境かと思います。特に執務時間についても厳密な決まりはないですので、各々の弁護士が、業務状況や自身の予定を踏まえ、自由に執務を行っていると思います。
休暇や早退等についても、基本的にはパートナー弁護士(理事)からあれこれ言われることはなく、自由に取ることのできる環境です。また、クラウドシステム等の導入により、在宅勤務でも事務所とほぼ変わらない執務が可能ですので、家庭の事情等に応じ、比較的自由に仕事を行っています。
あくまで私見ですが、コロナ禍後も安定して在宅・テレワークが併用できる弁護士事務所は(特に個人案件を扱っている事務所としては)珍しいのではないかと思います。
個人的な働き方としては、子供の保育園の送迎等もありますので、早朝や夜間について事務所で執務することはあまりありません。帰宅後自宅で業務をすることもありますが、深夜・夜間に日常的に業務を行っているという状況ではありません。
―― 事務所内でのサポート体制やチームの雰囲気について教えてください。
当事務所では、一定期間(事務所状況にもよりますが、最低1年)は、パートナー弁護士の相談や打ち合わせに同席し、協働して業務を行う体制となっています。
また、新人研修として、典型的な数分野について、事務所の弁護士が個人的に研修を行うことにもなっています。
弁護士の職務は専門的な部分が多く、かつ経験知によるところも多いといえますので、新人弁護士が1人で全てを進めていくのは現実的ではありません。その意味では、当事務所は、弁護士が「独り立ち」するまで、きちんとサポートしてもらえる体制が整っているといえます。
また、担当弁護士以外にもチャットツール・電話等で質問は可能ですし、月1で全支所の弁護士が参加する案件に関する相談会が開催されているほか、分野ごとの定期・不定期の勉強会も開催されています。
私の所属する東京事務所も含め、特に支所は弁護士数が少ないですが、所属する支所以外の弁護士に対するものも含め、相談は比較的しやすい環境にはあるかと思います。クラウドシステムにより案件・事件記録の一括管理がなされており、他の弁護士の担当案件にもアクセスが可能なので、他の弁護士が過去担当した類似案件の書面や進め方をシステムで調べ、参考にすることも可能です。
このほか、定期的に、パートナー弁護士(理事)との1on1面談の機会も設けられております。こちらでは、案件に関するものに限らず、現在の業務状況や悩み、今後のキャリアや業務開拓など、幅広い話題についてざっくばらんにお話しできますので、1人で抱え込んでしまうことにはなりにくい体制なのではないかと思います。
チームの雰囲気についても、雑談等も含め弁護士・事務局の隔たりなく行えていますので、総合的に見て良いのではないかと思います。
―― 自分自身が成長を実感できた瞬間を教えてください。
月並みですが、主として自分1人担当の事件について、見通しが厳しい事件を一応の決着・解決に導くことができた時は、成長を実感します。
未来の同僚へのメッセージ
―― 弁護士として成長するために、大切にしていることは何ですか?
「同じ事件は一つとしてない」という点を忘れないように心がけています。
法的な見立て、という意味では類似した事件であったとしても、関係者のスタンスや依頼者・クライアントの意向により、異なるアプローチが求められることは当然ながらあります。
過去の経験は大事ですし、それにより助けられる部分も多々ありますが、経験に縛られすぎない、という点は常に意識しないといけない、と感じています。
―― どのような志を持った方に、一新総合法律事務所で働いてほしいですか?
「個人」としてだけでなく「組織(事務所)の一員」として働く意識を持った方に当事務所で働いていただきたいとは思っています。
―― 未来の同僚に向けたメッセージをお願いします。
日本国内(さらには、世界でも)弁護士事務所は多数ある中で、まずは当事務所を知っていただき、さらにはこの長いインタビューにもかかわらず、最後までお読みいただき、ありがとうございます。
他の事務所にもそれぞれ良いところがありますし、当事務所が他の事務所よりも明確に優れているとまでは言えないかもしれません。ただ、「一定期間事務所が継続していること」「1人のカリスマに頼らない事務所運営がなされていること」といった点から生まれる安定感は、当事務所のアピールポイントではないかと思います。
業務面においては、業務についての裁量が広いことや、新規の業務開拓にも肯定的であり、(特に最初の数年間について)売上に関するプレッシャーはあまりない、といった点は、実際に働く中で個人的にも良い部分と感じています。
最終的にはご自身が悔いの残らない選択をしていただければと思いますが、ご縁があり当事務所に入所いただけましたら、私のみならず事務所全体として、ご自身の成長のため、しっかりとサポートさせていただきたく思っております。
最後になりますが、ご入所いただいた際には、事務所の一員として共に成長し、最終的には互いに助け合える関係性になるよう、私としては願い、期待しています。